|
学習について
1.教科等年間授業時数配当表
1年間に各教科などで学習する時間です。学校の教育課程※1は,学習指導要領及び教育委員会が定める基準に従って校長が責任をもって編成しています。
また、平成21年度から、新しい学習指導要領※2にかわります。新しい教科書ができるまでの間、補助教材等を使って新しい内容を学習します。
標準的な授業時数は下記のようになっています。

・表中の総合は総合的な学習の時間、英語は外国語活動の略です。
・表中の網掛けは文部科学省の標準時数とは違っています。
1~4年の英語については、長浜市内の全小学校が「小学校英語教育課程特例校」となっており、特別に英語科の授業を行っています。また、5・6年についても標準時数を上回る時間設定となっています。そのために、総合的な学習の時間の一部を外国語活動として使用しています。
・障害児学級は学習指導要領に従い教育課程を作成して実施しています。
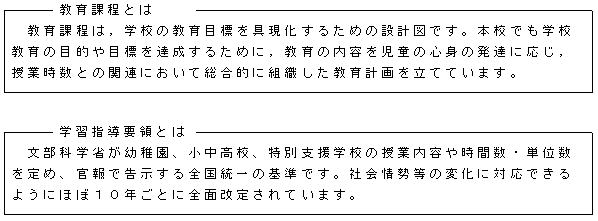
3.「総合的な学習の時間」ってどんなもの?
「総合的な学習の時間」とは、学習指導要領の改訂にともなって、2002年度(平成14年度)から始まった学習で、3年生から始まります。
学習指導要領に示されている総合的な学習の時間のねらいとしては、
①自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問 題解決する資質や能力を育てること
②学び方や、ものの考え方を身につけること
③問題の解決や探求活動に主体的、創造的・協同的に取り組む態度を育成 すること
④自己の生き方を考えることができるようにすること
などがあげられています。つまり、「知識」よりも自分自身で自主的に学ぶ「方法」や「態度」を身につけさせることに重点が置かれていることが特徴です。教科書のない自由なカリキュラムなので、各学年でさまざまな取組みがおこなわれています。
内容によっては保護者の方に集まっていただいて発表会をしたり、ボランティアを募集したりすることもあります。学年便りなどでお知らせしますので、ご協力をお願いします。
*長浜市内の全小学校が「小学校英語教育課程特例校」となっており、英語科の授業を行 っています。そのために、総合的な学習の時間の一部を英語として学習しています。
4.お姉ちゃんの教科書と違う!
教科書検定とは4年に一度、出版社が作った本が教科書にふさわしいかを文部科学省が審査する制度です。検定周期は4年以上となっています。
検定を通った教科書は各地域で検討され、次の4年間どこの出版社の教科書を使うかという教科書採択で決まります。県教委の指導により採択地区内市町教育委員会が共同して教科書を採択することになっています。(私立学校を含む)滋賀県ではその採択地区が国立・私立学校を含めて8つあり、最大8種類の採択が行われることになります。採択地区とは、その区域内で同一の教科書を使用することが適当と考えられる地域であり、県教委が自然的、経済的、文化的条件を考慮して決定することとなっています。採択地区が違えば教科書も違ってきます。
湯田小学校は第5地区(長浜市・米原市)となっています。
5.1年生から英語を学習するのですか?
長浜市では、教育特区の認定を受けた平成16年4月より、正規教科として、小学校に英語授業の導入を開始することを決定したことを受け、「総合的な学習の時間」の中で、英語の授業を実施しています。また、平成21年度より長浜市内の全小学校が「小学校英語教育課程特例校」となっており、特別に英語科の授業を行っています。
新しい学習指導要領においても、外国語活動が新設されました。本校では、長浜市教育委員会の策定したカリキュラムに従って学習を行っています。
長浜市の英語科の目標
英語に慣れ親しむ中で、聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を培うとともに、英語や外国の文化に対する関心や理解を深め、豊かな国際感覚を養い、世界の人々と積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成する。
キーワードとして「自立」と「共生」が示されています。 |
6.食育について
近年、子どもたちを取り巻く社会環境の変化などに伴い、朝食の欠食率の増加や偏った栄養摂取などの食生活の乱れや肥満傾向の増大などの「食」に関するさまざまな健康問題が増加しています。
また、食育基本法の制定により、健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむため、学校における食育の推進が強く求められています。
成長期にある子どもたちにとって、健全な食生活は健康な心身をはぐくむむために不可欠であるとともに、将来の食習慣の形成において極めて重要です。
そこで、本校でも教育活動全体をとおして、知識としてだけでなく、望ましい食習慣を実践する態度を育成する必要があると考え取組みをすすめています。児童生徒の発達段階に応じた年間指導計画を作成し、全教職員共通理解のもと、各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間等教育活動全体で食に関する指導に取り組んでいます。
また、学校給食を「生きた教材」としてさまざまな学習に活用し、効果的な食に関する指導を行うこと、さらには、日常の食生活に生かす能力を育成するため、家庭や地域等と連携した食育を計画・実施しています。
特に、18年度から、小学校における「食育の日」(月1回)の推進をとおして、特色ある食育に取り組むとともに、子どもたちの健康の状況を踏まえた、組織的・計画的・継続的な食育を行っています。
また、5年生が実施する「びわ湖フローティングスクール」では、「うみのこ」での食事や「びわ湖環境学習」をとおして、いのちの恵みや郷土の食文化を知るとともに、友情や助け合い・協力の態度をはぐくむ食育にも積極的に取り組んでいます。
食に関する指導は、学級担任や学校栄養職員による学級活動や、学校栄養職員の特別非常勤講師制度を利用した授業を通して行ってきています。
さらにPTA活動の中で保護者と共に活動することを大きな柱としながら、様々な組織や団体との連携を図っていきたいと考えています。
7.特別支援教育が始まると聞いたのですが・・・
学校教育法が2006年6月に改正され、2007年4月1日からの特別支援教育完全実施により、これまでの「障害児学級」に代わって、「特別支援学級」という名称になっています。
特別支援教育とは、障害のある子どもたちが自立し、社会参加するために必要な力を培うために、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その可能性を最大限に伸ばし、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導および必要な支援を行うものです。
本校の特別支援の基本
「一人ひとりに、でき得る限りその子に応じた学習の場および状況を提供する」という考えで、全教育活動の中核をなすものであり、全校的な取り組みを進めていく。 |
また、学習障害(LD)(注1)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)(注2)、高機能自閉症(注3)自閉症(注4)等、学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒数について、文部科学省が平成14年に実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」の結果では、約6パーセント程度の割合で通常の学級に在籍しているというデータがあります。
特別支援教育を取り巻く最近の動向として、児童生徒の障害の重度・重複化や多様化、より軽度の障害のある児童生徒の対応や早期からの教育的対応に関する要望の高まり、高等部への進学率の上昇、卒業後の進路の多様化、ノーマライゼーション(注5)の進展などが進んでいます。
今後、国では、一人ひとりの教育的ニーズを踏まえて適切な教育を行うとの考え方を示しました。これを受けて柔軟で弾力的な制度の再構築、教員の専門性の向上と関係者・機関の連携による質の高い教育のためのシステムづくりが進められています。
本校でも総合的な支援体制の確立を目指し取組みを進めています。
「特殊教育」から「特別支援教育」への転換を図るには,障害のある児童一人ひとりの教育的ニーズを明らかにし、それに確実にこたえていく実践を進めていかなければならず、そのためには、制度上の改革だけでなく、学校をあげての支援体制を構築し,担当教員が高い専門性を発揮していくことが求められています。
主な発達障害の定義について
発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
主な発達障害の定義です。
(平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より作成)
注1 学習障害(LD)の定義〈Learning Disabilities〉
学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。
学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。
注2 注意欠陥多動性障害(ADHD)の定義〈Attention‐Deficit/Hyperactivity Disorder〉
注意欠陥多動性障害とは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。
また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。
注3 自閉症の定義〈Autistic Disorder〉
自閉症とは、3歳位までに現れ、(1)他人との社会的関係の形成の困難さ、(2)言葉の発達の遅れ、(3)興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。
注4 高機能自閉症の定義〈High‐Functioning Autism〉
高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、(1)他人との社会的関係の形成の困難さ、(2)言葉の発達の遅れ、(3)興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。
また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。
注5 ノーマライゼーション
障害のある者も障害のない者も同じように社会の一員として社会活動に参加し、自立して生活することのできる社会を目指すという理念。
※アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されるものである。
8.人権教育について
県では国内外の人権尊重の気運の高まりと取組みの中で、平成15年3月に「滋賀県人権施策基本方針」が制定されました。これを受けて、同和教育の取組みや、その深まりと広がりを求めた実践で培われた成果と手法を評価しながら、同3月に「人権教育推進プラン」が策定され、その徹底が図られています。
また、平成16年3月に策定された「人権意識高揚のための教育・啓発基本計画」も踏まえながら、日々の実践を積み重ねることが必要だと考え取組をすすめています。
本校でも、県や市の施策をふまえ人権教育を推進しています。誰もが自他の人権を尊重し、自分の能力を発揮して自己実現を図り、人と人とが豊かにつながり共に生きようとする児童生徒の育成を目指すものです。
そのために、人権教育推進プランおよび本校の人権教育計画に基づき、全領域にわたる取組みの中で、人権感覚を高め、人権問題についての正しい理解・認識を培い、人権尊重の実践的態度を育成することに努めています。
保護者のガイドブックTOPへ戻る
|
